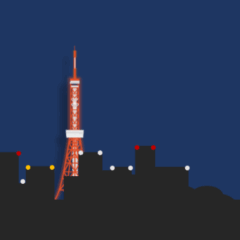徹夜でZINEを作る。たぶん帰宅したときには0時を回っていて、シャワーを浴びたり一息ついたりしているうちに1時になって、ようやく原稿と向き合った。集めた原稿の流し込みは終えていたので校正をひと通りして、執筆者紹介を書いて、目次を付けてから最後に自分のエッセイを書いた。筆が乗って、これならもう少し書けそうだな、と思ったところで空が明るくなっていることに気づいたので区切りとし、身も蓋もなくエッセイに「助けてください!」という題を付けた。校了。部屋のプリンターで40部を印刷する。コピー用紙はコンビニで調達できるので良いとして、予備のないトナーの交換時期が不安だったが持ちこたえてくれた。絶え間なく動くコピー機の音をBGMに、床に転がって90分だけ寝た。
けたたましく鳴るアラームに抗いながらなんとか起きる。セブンイレブンのコピー機でカラーの表紙を刷り、また家に戻って30部ほど本文を印刷しながら中綴じ用のホッチキスで製本をしてゆくと、即席ながらZINEとしてはなかなかいいんじゃないですか、という出来のものが完成した。製本していない分は現地で綴じればいいや、と思いホッチキスをバックパックにぶち込み、大量の刷り上がりをどうしよう、と思ったところ、玄関にあった靴箱が丁度よい大きさだったのでそれに入れ、開かないように養生テープでぐるぐる巻きにしておいた。設営用の道具を適当にかき集め、満載のバックパックとキャリーケースを引きずり、会場へ。遅延していたりんかい線は満員電車で、いかにもハレの日です、という服装の人が多かった。こんなに文学の民が動員されているのか、と驚いたが半数が東京テレポートで降りて行った、お台場に行くのだろう。スラムダンクのファンらしき子供たちが騒いでいた。
駅前で待っていると、見慣れた柄シャツにジャケット、リーゼントに丸いサングラス、という男が扇子を仰ぎながらこちらに近寄って来て、佐藤くんだと一目で分かった。暑くなることを見越して僕もアロハシャツにサングラスだったので、図らずもペアルックになってウケた。ある夏の日、佐藤くんもワカオくんも僕も、皆が偶々同じような柄シャツで大学に来て同じ授業を受けていたことがあり、その時はさすがに面白くて廊下で3人の写真を撮ってもらった。三田にアロハで来る奴らはあんまりいない。育ちの良さそうな男子はもれなくラルフローレンのポロシャツに短パンにテニス・シューズ、という格好で、僕は彼らにけっこう好意的、というかむしろ憧れすらあるのだけれど、いったい何が発祥なのかと思って調べたら、50年代の「アイビーリーグ」というアメリカの上流階級にルーツがあるらしい。そのスタイルが日本に輸入され、何度かの流行を経て今に至るようだ。うちの大学のポロシャツ君たちは、不思議とみな同じような顔をしている。眉毛が太くて凛々しい。
南展示場へ続く長い長い通路は羽田空港の第2ターミナルを思わせた。4度めの出店ともなれば今さら高揚感も緊張もない。佐藤くんと手分けして粛々と設営をする。今回の会場は、前に比べてだいぶ広々としているように感じ、同じビッグサイトでも建屋が違うとこんなに快適なのか、という印象を受けた。まず照明が明るく、天井が高い。「今日は酸素がある文フリだった。地球でおこなわれていたころの文フリを彷彿とさせる回だった。」というツイートが流れてきて激しく同意したが、まさしくその通りだと思う。前回の反省を踏まえてか通路は広く、出店ブースになる長机のあいだにも人が通れるようなスペースが確保されていた。これよ、これを求めていたんよ、という感じである。地球でおこなわれていたころ――というのはおそらく2023年頃までの話だと思うが(そのあたりを境に酸素が極端に薄くなった)、今回は僕らのブースがたまたま広い通路に面していたということもあり、周りの出店者や導線に過剰に気を遣うことなく、伸び伸びと「お店を広げる」ことができたというのは、まさしく運営側の尽力によるものだろう。
とはいえ出店者の数は過去最高を更新し続けている。「こんなに広いの!?」と驚くような巨大空間がふたつ分、文フリの会場になっている。僕らのブースは上の階にあったのでその限りではないが、下の階へ降りてゆくエスカレータからは会場全体が一望できて度肝を抜かれた。各ブースはエントリー時に申告したカテゴリ(「小説」とか「短歌」とか「評論」などといったあれこれ)によって分けられ、同ジャンルによっていわゆる「島」が形成される。我々は「文藝誌」を名乗りつつも毎回「エッセイ・ノンフィクション」の島にいるが、それは一応エッセイを主軸に置いていることと、僕に日記繋がりの知り合いが多いことが理由である。すると周りにフォロワーや顔馴染が多く、作品を買いに来てもらうことはもちろん、自分がブースを離れて同じ界隈の知人に会いに行く際も非常に楽で、動きやすい。しかしその分、僕が他のカテゴリの様子を見に行ったり買いに行ったりする暇と余裕がほとんどなくなってしまい、知人の中でも「絶対に挨拶しておかなければ」という3,4人に会いに行くだけで精一杯であった。一度遠くのブースにいる知人を尋ねてから「あ、この近くにあの人もいたんだ……」と気づいてからではもう遅い、流石に戻る時間も気力もなく、泣く泣く諦めて買えなかった本はいくつもある。自分で出店している限り、もう純粋なお客さんには戻れないのだと思うと寂しい気もする。もちろん、仲間や友人に売り子をしてもらうとはいえ(今回はタマムラくんが来てくれて、無理を言って急遽売り子をしてもらった)、自分のブースは常に気掛かりだし、なによりもブースを「お金と作品を交換するだけの場」にはしたくない。ただでさえ本という得体の知れない紙の束に、原価や相場も定かではないような値段をつけて売っているのだから、お客さんに対しては「わかりやすく」あることや、お金を払うだけの価値があると感じてもらうことが大切だと常々思っている。それこそが文フリの難しく、面白いところだろう。
偉そうなことを書いてしまったが、僕もトライ・アンド・エラーで文フリに出続けている。今回も「こんなもんか」というくらいしか売れていない。出る度に後悔や反省点を挙げればきりがない。そもそも何のためにこういうことをやっているんだっけ、と根本的なことを考えさせられてばかりだ。文学フリマという「巨大」市場の中で、参加することに意義がある、と主張する人が沢山いるのは重々承知しているが、それでも僕は、僕らが書いたものをできる限り多くの人に読んでもらいたいし、そのためには多くの人に作品を買ってもらう必要があると思っている。いくらインディーズとはいえ、自分たちの美学を追求しているだけでは誰にも手に取ってもらえない。どんな文章が優れているか、と感じるのは人それぞれだし、会場においてお客さんが「買う」と判断する決め手はその文章そのものではなく、どんな文章が「書いてありそうか」でしかない。そして、それを左右するのは売り手のプロモーションであり、本の装丁であり、ブースの雰囲気でもあるのだ。僕ひとりで書いたものを僕が売るならまだしも、今となっては仲間がいる。彼らの文章を僕が売り手として引き受けている以上、「もっとやれたな」という反省と、「次はもっと売るから」という自負を今は強く感じているし、そこから湧いてくる新たなアイデアと、同時に諦めなければいけないこともいっぱいあるだろう。そして今のところ、それを考えるのは結構楽しい。やりたいことばかりだ。
***
毎度のことながら、ブースに来てくれた方、会場でお会いした方、会場には来られなくても告知に反応をくださった方、蔭ながら応援してくださった方、皆さんに感謝しています。いつもありがとうございます。そして、何かをきっかけに初めてこの日記を読んでくださっている方、本当にありがとうございます。今後も文章でなにか愉快なことをお届けできればな、と思ってこれからも書いてゆきますので、どうぞよろしくお願いします。
本来この日記やTwitterのアカウントはもっとハードボイルドなものにするつもりで、自我を出すまいか、おれの文章は誰かに読まれたいと思って書いとらん、おれは媚びを売らずにまとまった文章だけでやってゆくんじゃあ、おんどりゃー舐めんなよ、と変な方向に尖った意気込み方をしていたのですが、最近いろいろな人と話す中で「だいぶ尖ってたな~」と思い直すようになり、フレンドリーな感じを前面に出していこうという気になっています。無理にカッコつけても本当にしょうがない、おれは弱い人間です。