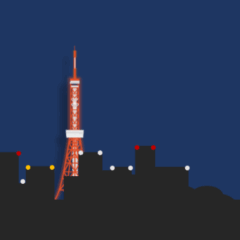神宮球場へ。神宮といえばこの話だ。
小説を書こうと思い立った日時はピンポイントで特定できる。1978年4月1日の午後一時半前後だ。その日、神宮球場の外野席で一人でビールを飲みながら野球を観戦していた。神宮球場は住んでいたアパートから歩いてすぐのところにあり、僕は当時からかなり熱心なヤクルト・スワローズのファンだった。空には雲ひとつなく、風は暖かく、文句のつけようのない素敵な春の一日だった。そのころの神宮球場の外野にはベンチシートがなく、斜面にただ芝生が広がっているだけだった。その芝生に寝転んで、冷たいビールをすすり、ときどき空を見上げながらのんびりと試合を眺めていた。観客は――いつものように――多くはなかった。
村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』2007, 文藝春秋, p.49(文庫版)
1回の裏にデイブ・ヒルトンがタイムリーを打った瞬間、「そうだ、小説を書いてみよう」という天啓が村上に降りてきた――というのはよく知られた話で、あまりにも出来すぎているというか洒落臭いのでおれは全くの嘘だと思っているが、一応そういうことになっている。どうせその前から習作を書き溜めていたに違いない、本当は新人賞にも出し続けていたんじゃないか、しかしそれでは彼なりに恰好がつかないのだろう、「おれ全然勉強してないんだよね」とテストの日に言う奴みたいだ、と喩えるのは無粋だろうか。
今日はビールが半額の日で、半額というと450円、450円というのは四捨五入するとタダなので何も考えず馬鹿みたいに飲んだ。同行した先輩がスワローズ・ファンである手前、僕も中古のユニフォームを羽織って応援歌に手拍子を合わせていたが、全くつまらない試合だった。横浜のエースである東克樹から点が取れる気配は一切なく、僕らは観戦もそこそこにひたすらビールのカップを積み重ね、裏の喫煙所で駄弁っていた。ヤクルトは当たり前のように完封で負けた。帰路、缶チューハイを煽りながら渋谷駅まで歩く途中にどういう訳か先輩と喧嘩になり、人目も憚らず怒声を浴びせ合って別れた。