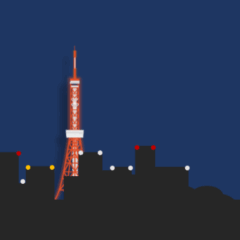いつだったか高松の場末にあるコーヒースタンドで世間話をしていて、たしかその一年前にも同じ店に立ち寄ったからお久しぶりです、覚えてますか、ああ、あの時の、みたいな話をした記憶がある。香川の高松だ。それで二度目に行った時には大柄な、店主と同じやはり大柄な男がいて、彼は何処かの地方新聞社で記者をやっていたのだと名乗り、ええ新聞ですか、興味あります、と言った僕に「新聞なんてもう終わりだよ」と言った。それに対して僕はなんと言ったかもう忘れたけれど三人で盛り上がって、またいつか来ます、忘れた頃に、と僕は店を出て50メートルほど歩いてからコーヒーの代金を払っていないことに気づき、ふたたび戻って小銭を店主に渡してごめんなさい忘れてましたと言ったら引き換えにチョコボールを貰った。店主は僕に「君は良い眼をしてる、俺には分かる、だから名前を敢えて訊かないでおくよ」と言った。彼はNASAのロゴが付いたMA-1を着ていて、スペースシャトルのミッションごとに作られたワッペンが腕のところに幾つか刺繍されていたのが僕は気になって、「そういうの好きなんですか」と訊いたら、「いやあ格好いいでしょう、昨日僕の誕生日でね、奥さんに貰ったんだ」と嬉しそうに言っていた。珍しくサイフォンで珈琲を淹れる店だった。出来上がった珈琲は熱いまま紙のカップに注がれて冷めるまでにだいぶ時間がかかったので、僕はこの後に乗る予定の特急の時間を何度も気にしなければいけなかった。フヅクエのソファ席で『百年と一日』を読んでいたらそんな記憶が蘇ってきて、それは海辺の街の話があったからかもしれず、手元から目を離して棚の本の背表紙と窓に映る電灯の明かりをぼやっと見つめていると、僕はこの数年間、確かにそれだけを信じて生きてきたのだと思った。